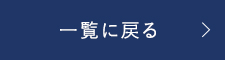【AICE連載セミナー】太陽光発電が持続的な長期安定電源となるために(大関 崇 第3回)
- コラム
2025.07.04
【AICE連載セミナー】太陽光発電が持続的な長期安定電源となるために(大関 崇 第3回)

大関様に執筆頂いた記事を、4回に分けて掲載いたします。
●第3回:太陽光発電が持続的な長期安定電源となるために
第4回:2050年カーボンニュートラル実現に向けた太陽光発電の役割
著者 大関 崇
(国立研究開発法人 産業技術総合研究所
再生可能エネルギー研究センター 太陽光システムチーム)
4.持続的な長期安定電源化へ
4.1 運用管理
ここからは、導入後の持続的な長期安定電源化に向けての課題と展望を述べます。太陽光発電は発電事業であるため、民間の事業性の中で導入・運用を行いつつ、国レベルではエネルギー政策として展開していく必要があります。持続的な発電事業を継続させるためには、事業性とリスク低減の両立が重要です。昨今の事故は設計・施工の要因が多いですが、設計から運用を含めた全体の最適化がより重要となってきます。また、電力の保守人材の不足が懸念されており(人材不足はこの分野に限った話ではないが)、例えば、電気主任技術者は2030年に第2種において約1,000人不足、第3種において約800人の不足が発生し、2050年に向けて人材不足は拡大することが試算されています71)。このような背景から、費用便益評価によるリスク低減対策の最適化、人材不足を補う方策として、スマート保安が検討されています。現在、維持管理費は、約0.5万円/kW/年17)であり、単純計算で10万円/kW(20年計算)、約3.8円/kWh(設備利用率15%で試算)であり、太陽光発電の目標である発電コスト7円/kWhの半分程度を占めることになります。このコスト低減の考え方は、人が必要な作業を減らすことが有効であり、それには現場頻度を減らす、もしくは現場作業を効率化することになるため、その実現のための技術開発が求められています。すでにスマート保安アクションプラン等により技術導入割合のKPIが業界ごとに設定され72)、フォローアップもされていますが73)、現状は保守点検時の効率化のみの検討となっています。これは、定期点検などの現地確認項目を直接代替する(例えば、目視の代わりにカメラを設置する)などの検討にとどまっていることを意味しています。本来は、設計において担うリスク、保守管理において担うリスクの最適化が重要です。そのため設計時のリスク評価をしたうえで、そのリスク事象を常時監視装置により発見するようなCBM(Condition base maintenance)に移行する必要がありますが、考え方も含めて十分な整理はされていません。このシステムの実現には、設計段階から廃棄まで一気通貫で評価、運用する必要があるため、設計時からのDX化、多数分散型および寡少シェアによる分散したナレッジと事象の収集、現地で発生している事象とのアノテーション、それらデータの集約化が大きな課題と考えています。知見の集積と最適化のフィードバックを実現することにより、各断面において意思決定可能なシステム技術74)を開発することにより、本来のスマート保安を実現できると考えられます。このような技術を活用して、常時監視装置による定期点検の延伸という規制緩和の仕組みは、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のスマート保安プロモーション委員会75)の活用等により制度上可能でありますが、現状は太陽光発電のメリットはそこまで明確ではないため、十分に進んでいません。今後は、電気主任技術者の2時間駆け付けの緩和などとも含めて、本来あるべき姿、特に地上設置型の太陽光発電は、人が滞在する需要設備と異なり、他者加害性や波及事故リスクの評価と適切な経済性の確保の検討が重要な課題です。また、安全面以外にも発電性能の評価において、スマートメータなどを活用した経済的な発電特性モニタリングとAI等を利用したデータ分析手法76、77)、などが低圧発電設備まで広く利用されることが必要と考えています。
更に事業継続の観点として、事業承継やリパワリングが重要となってきます。開発した土地や系統の有効利用の観点から、既存の発電所については、安全性確保を大前提として、積極的に継続利用することが望まれます。国内では、FIT後の継続意思の有無の調査として、積極的と回答したのは77~67%、リプレイス想定と回答したのは50~40%という結果があります78)。市場の太陽電池モジュールは、過去に導入されたものと比べて、変換効率が1.3~1.4倍となっていることから、面積当たりの発電特性も増加します。これにあわせた電気設計、また構造の補強や補修などの技術開発が重要となります79)。また、徐々に発電特性が低下していく中で、どのタイミングでどのような内容のリパワリングを実施するかの意志決定ツールの開発が重要となると考えています80)。その実現には、現状特性の簡易把握技術、DXを活用した再設計技術、それをもとにした長期発電電力量の予測技術の組合せが必要となります。
4.2 End of Life
最終的な機器の排出段階では、適切に廃棄されることが重要ですが、将来的には資源循環の考えのもと、リサイクル中心になると想定されます。現状の排出量の試算は、2036年ごろに太陽電池モジュールが17~28万トンと見込まれています。廃棄リサイクルの課題については、経産省、環境省の「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」において、中間とりまとめがなされ、トレーサビリティの確保、放置された場合の対処、費用負担などの課題が整理されたところです81)。この中でも太陽電池モジュールの重量の6割程度がガラスであることから、ガラスのマテリアルとしてリサイクルが課題となっています。現状はガラス分離・回収技術として、燃焼/熱分解、水平切断(ホットナイフ等)、ガラス研削回収、ブラスト/ハンマー、EVA/Cellシート研削、ウォータージェットなどさまざまありますが、板ガラスまで戻せる技術の検討は一部実施されているものの、実用化には更なる検討が必要となります。また、ガラス、シリコンについては、最終的にどこの段階までリサイクル、リユースなどするかは、制度的かつ技術的な課題として今後整理する必要があります82)。特に現在の海外輸入品が主である国内市場を鑑みると、太陽電池モジュールにおけるclosed-loopを形成するにはハードルが高いため、カスケード利用も含めた社会システム設計が必要となってきます。その際には、資源循環、エネルギーとしてのLCA、廃棄量等、様々なメトリックスにおいて、長寿命化や高効率利用、マテリアルリサイクルレベルなど各種シナリオごとの評価を実施することが重要となってきます83)。
4.3 持続的な発電事業のための電源価値向上
持続的な発電事業を継続するためには、エネルギー事業としてどのように収益を得るかについて考える必要があります。現状は、FIT/FIP(補助額上乗せ方式)やPPAなどによりkWhによる収益は基本となっています。今後は、FIPに代表されるように電力市場への統合が進んでいくことが想定されます。その際、現状でも昼間の電力市場のスポット価格が最低価格の0.01円となる時間が増加しており、昼間の電力・エネルギー価値が低下しています。太陽光発電は単独では、昼間にしか発電できないため、昼間のkWh以外の電源としての価値を向上させることが必要となります。エネルギーシステム全体から見た場合、例えば第6次エネルギー基本計画においては、統合コストが試算されています19)。ここでの統合コストは必要となる柔軟性の一部の試算でしかありませんが、このコスト負担をどのように行うかの議論は、発電事業者からの視点では重要となります。これらの対策方法として、大きく発電事業者側が対策する方法と、一般送配電事業の系統側の対策する方法があります。発電事業者側の対策の場合、費用負担する方法として、系統接続要件として義務的とする方法と、柔軟性の機能を市場でマネタイズする方法があります。また、系統側対策としては、費用負担方法として、託送料金やマスタープランのように賦課金方式で社会的に負担する方法があります。グリッドコード検討会84)では、機能として具備するものとその価値のやり取りは別であるとの議論がなされていることから、市場でやり取りされることも想定し、発電事業者としては、積極的に電源価値を向上させ、その柔軟性をマネタイズすることが持続的な発電事業につながると考えられます。
電源価値向上の基本的な考え方は、短期、長期的な変動性が持つVUCA(Volatility、 Uncertainly、 Complexity、 Ambiguity)をいかに予見可能性なものにできるかが鍵となります。方法としては、蓄電池などの蓄エネデバイスの利用がありますが、これは蓄電池等のコストダウンに依存するところは大きいです。その他には、アグリゲーションによる変動緩和85)、発電予測技術開発による不確実性の低減による価値向上86、87)、太陽光発電自ら慣性力88)やLFSM-O(Frequency-Watt) 89、90)などの柔軟性を提供することが考えられます。
また、個々の発電事業者の視点に加えて、例えばすべての太陽光発電が柔軟性を提供することにより、火力の台数やLFC容量分を低減することで、全体の出力制御量を低減できるといった試算もあることから91、92)、社会全体の便益向上と発電事業者の便益の両立(価値の適正配分)が可能な制度やシステム、それを実現する技術開発が将来的には必要となると考えています。
参考文献
17)調達価格等算定委員会「令和6年度以降の調達価格等に関する意見」について
19)資源エネルギー庁, 長期エネルギー需給見通し 関連資料, 平成27年
71)第14回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ
72)電気保安分野 スマート保安アクションプラン
73)令和4 年度電気保安のスマート化推進に関する業界 別推進状況の把握調査・分析業務報告書
74)TRUST PV Project https://trust-pv.eu/
75)www.nite.go.jp/gcet/tso/smart_hoan_shiryo.html
76)IEA PVPS TASK 13, The Use of Advanced Algorithms in PV Failure Monitoring
77)J.A.Vasquez , A New Approach for Filtering PV Performance Data Based on Acceptance Bands Around the Ideal PV System Power, WCPEC 8th, 2022
78)令和3年度 再生可能エネルギー固定価格買取制度における賦課金単価算定の精緻化に向けた分析等調査
79)NEDO太陽光発電主力電源化推進技術開発 事業原簿:関西電力,CO2O,エクソル,日本地工,アジア航測
80)NREL, Best Practices at the End of the Photovoltaic System Performance Period
81)再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会 中間取りまとめ
82)DOE, Solar Futures Study, 2021
83)Heather Mirletz, More than recycling: The importance of multiple metrics for a Circular Economy for PV in the Energy Transition, 40th EUPVSEC
84)https://www.occto.or.jp/iinkai/gridcode/
85)再生可能エネルギーアグリゲーション実証事業
86)日本気象協会, NEDO 2022年度中間年報 発電量の短期予測に向けた日射量予測技術の開発(日射量の短期予測に関する研究開発)
87)日本気象協会,産業技術総合研究所, NEDO 2022年度中間年報翌日および翌々日程度先の日射量予測技術の開発
88)再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発(STREAMプロジェクト)
89)NREL Demonstration of Essential Reliability Services by a 300-MW Solar Photovoltaic Power Plant
90)産業技術総合研究所,東京理科大学,東芝エネルギーシステムズ株式会社, 2021年度中間年報 太陽光発電による調整力創出技術の実証研究
91)占部他,風力発電と火力発電の協調した調整力提供の検討, エネルギー・資源学会論文誌,44巻(5),2023
92)石井他,太陽光・風力発電からの電力需給調整力提供による経済的・環境的効果,電気学会新エネルギー・環境研究会, 2021年