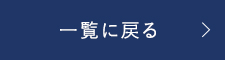【AICE連載セミナー】2050年カーボンニュートラル実現に向けた太陽光発電の役割(大関 崇 第4回)
- コラム
2025.07.25
【AICE連載セミナー】2050年カーボンニュートラル実現に向けた太陽光発電の役割(大関 崇 第4回)

大関様に執筆頂いた記事を、4回に分けて掲載いたします。
●第4回:2050年カーボンニュートラル実現に向けた太陽光発電の役割
著者 大関 崇
(国立研究開発法人 産業技術総合研究所
再生可能エネルギー研究センター 太陽光システムチーム)
5.2050年に向けて
更なる導入拡大に向けては、さまざまなエネルギーシステムの分析がなされている。例えば、OCCTO(電力広域的運営推進機関)の「将来の電力需給シナリオに関する検討会」における分析の一例としては、2050年には約300GWを超える太陽光発電の導入量も想定されています93)。太陽光発電協会のビジョンにおいても同様に2050年には386GWの導入量見通しを公開しています94)。このスケールになると、昼間には圧倒的な余剰が発生することが容易に想定されます。OCCTOのマスタープランでは、太陽光発電が260GW導入想定において、需要立地誘導シナリオ時でも出力制御量は全国で24%です(系統増強前)95)。この電力の有効利用をどのようなシステムで実行するかを考える必要があります。その際2050年になると、人口減とエネルギーインフラの在り方も同時に検討が必要となってきます。電力需要が縮小するようなエリアに対して、ユニバーサルサービスをどのような方法で維持するか、例えば送配電を維持せず、蓄電池と太陽光発電のパッケージで実現し、部分的に撤退していく方法も一つのシナリオとしては考えられます48)。また、圧倒的な電力の余剰発生においては、設備コストが十分に下がっていれば、DC/AC比が相当高くして、クリッピングによる安定電源とみなすことも場合によっては考えられます。地域共生が大前提であるものの、将来の広大な未利用地が発生することを想定した場合、需要とのパッケージにおいて太陽光発電+植物工場、太陽光発電+データセンター、太陽光発電+水素プラントなどの利用もシステムとして想定されます。当然、それぞれのシステムにおいて、エネルギー源の太陽光発電は、どの程度のエネルギーコストで提供できるかを考える必要があります(例えば、水素20円/Nm3では、5円以下の電⼒調達コストが必要96)=太陽光発電の発電コスト)。海外の最安値の太陽光発電を考えると、大規模な土地と系統に依存しないシステムの発電コストは低コストのポテンシャルの想定できるため、このようなケーススタディやシステム検討は、今の段階から実施しておくことが肝要と考えています。
6.まとめ
太陽光発電の早期大量導入の展望と課題について概括しました。当面は、足元の安全性や地域共生の課題を解決しつつ。2030年のエネルギーミックスの実現に向けて、導入拡大を住宅、建物を中心に導入拡大し、将来的な地上設置の準備をしていく必要があります。それと並行して、太陽光発電のエネルギー価値が落ちていくなか、電源としての便益向上を行う技術開発やそれを活用する制度設計が必要となります。
2050年に向けては、太陽光発電が社会システムに影響を与えるレベルとなっており、エネルギー政策、地域政策を両立しつつカーボンニュートラルを実現するためには、社会科学、人文科学との連携も重要となってきます。太陽光発電が自由経済の中で、真の主力電源化を実現するために必要なことは、持続的な広義のイノベーション、インフラとして支える人材、そしてその人達のパッションです。
参考文献
48)経産省, ソーラーシンギュラリティの影響度等に関する調査報告書 : 平成29年度新エネルギー等導入促進基礎調査
93)OCCTO,第2回将来の電力需給シナリオに関する検討会
94)JPEA,太陽光発電産業の新ビジョン - “PV OUTLOOK 2050”
95)OCCTO,広域系統長期方針(広域連系系統のマスタープラン)別冊(資料編)
96)経産省, ⽔素を取り巻く国内外情勢と⽔素政策の現状について