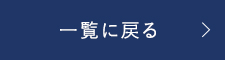【AICE連載セミナー】カーボンニュートラルを考える 第5回 主要国・地域のCN化への取組み アップデート(AICEアドバイザー 山本 博之)
- コラム
2025.08.08
【AICE連載セミナー】カーボンニュートラルを考える 第5回 主要国・地域のCN化への取組み アップデート(AICEアドバイザー 山本 博之)

AICEアドバイザー(元マツダ(株)技術研究所長) 山本 博之
本連載セミナーの最初に「カーボンニュートラル(CN)を考える」を寄稿させていただいて以来、2年ぶりの再登板です。今回は、主要国・地域のCN化への取組み状況をアップデートし(第5回)、CO2低減効果がより大きいCN技術を検討するためEVとエアコン(内燃機関ではありません!)を比較します(第6回)。
■ 2050CN目標は維持しながらも競争力強化に舵を切った欧州
世界のCNのリード役であるEUは、2025/5のプレスリリースで、2030年温室効果ガス(GHG)排出量の削減目標55%を達成見込みと発表しました1) 。加盟各国が提出した国家エネルギー・気候計画(NECP)の集計値は草案段階で51%削減に留まりましたが、より野心的な目標を求め最終版では54%に高めました。
しかしながら足元では、エネルギー価格の高騰やそれに伴う産業競争力の低下などの課題も顕在化しています。鳴り物入りで設立されたノースボルトの破産はその端的な例でしょう。欧州中央銀行総裁やイタリア首相を歴任したマリオ・ドラギ氏がまとめた通称ドラギレポート2)(2024/9)では、エネルギー多消費産業ほど生産量が低下していることを示し、欧州の高いエネルギーコストが欧州企業の成長の妨げになっていること、産業戦略の不足がクリーンテック分野の競合力を低下させていること、過度な規制や投資の不足がデジタル分野のイノベーション遅れを招いていることなどを指摘しています。その上で、経済安全保障のためのクリーンテック分野での中国依存低減ならびに産業戦略と政策協調によるEU域内投資の強化、脱炭素・エネルギー関連での技術中立の推進 成長戦略では年間7,500-8,000億ユーロの追加投資とEU共同債の発行 を提案しています。自動車関連では、「低排出ガス燃料の市場浸透率向上が、予想よりも遅いEVの普及を補う可能性」にも言及しています。
ドラギレポートを受けEU委員会は、米中とのイノベーションギャップの是正、脱炭素と競争力強化のための工程表、域外依存低減と安全保障強化 を示したEU競争⼒コンパス3)を発表しました(2025/1)。また、2025/3には競争力コンパスの一部としてEUクリーン産業ディール4)を発表し、2050CN目標は据え置いたまま技術中立の原則に基づいてエネルギー多消費産業とクリーンテックへの支援を示しました。このディールの副題にも「競争力」が含まれています。誇り高い欧州が面子も守りながら、競争力をより強く意識した現実路線に軌道修正したようです。
■ 競争力強化にひた走るアメリカ
米国は2024/12に、2035年までにGHGの61-66%削減を次期NDC(国が決定する貢献)として国連に提出しました。しかしながらわずか1か月後にはトランプ大統領が就任し、その日にパリ協定再離脱の大統領令に署名しました。就任演説では「国家エネルギー非常事態宣言」を行う方針を示し、化石燃料に対して” Drill, baby, drill ! ” として採掘を奨励しました。石炭産業を復活させる大統領令にも署名し(2025/4)、採掘、輸出、石炭火力発電を支援するとしています。2025/5には原子力に対しても大型炉の新設、規制緩和、承認迅速化、輸出強化などを目的とした大統領令に署名しています5)。
一方、IRA(Inflation Reduction Act, インフレ抑制法)による資金配分を一時停止した上で、EV購入、エネルギー効率化住宅、クリーン電力製造、クリーン水素製造などのエネルギー関連税額控除の廃止または段階的廃止法案を提出しています6)。洋上風力発電についても就任時に新規承認を停止しています。これらは国家エネルギー非常事態宣言と矛盾し、化石燃料産業への配慮かと穿った見方をしがちですが、より安価なエネルギーを大量に確保し、競争力とエネルギー安全保障をさらに強化するスタンスに思えます。
州、市、個別企業のレベルでは、再エネ供給・利用の拡大や建築物脱炭素化などのCNへの取り組みは継続しているようです。その一方で、カリフォルニア州のEV促進規制を無効とする決議が連邦上下院で可決され、大統領令署名(2025/6)を経て法的拘束力を持ちました。カリフォルニアを含む11州が早速、提訴しており、暫くは政治的対立の影響が続きそうです。
■ 再エネ導入が急速に進むも化石燃料利用も伸長する中国
習近平国家主席が2020年に掲げた「3060目標」(2030年までにCO2排出量ピークアウト、2060年までにCN)達成のため、中期的なロードマップとして第14次5カ年計画(2021-2025年)が策定されています。5カ年計画の最終段階として、中国国務院は2024/5に「2024-2025省エネおよび炭素削減行動計画」7)を示しました。非化石エネルギー割合は、2024年18.9%、2025年20%とし、そのために 化石エネルギー使用量の削減と代替化、非化石エネルギーの消費拡大に向けた取り組み、鉄鋼業、石油化学産業、交通など8分野における省エネルギー・低炭素化活動 を掲げています。具体的な施策としては、小規模な石炭火力や石炭炊きボイラーの廃絶、シェールやタイトなどの非在来型石油・ガスの大規模開発、砂漠での大規模風力・PV発電基地の建設加速、中型・大型トラック、オフロード移動機械の新エネルギー推進などを示しています。砂漠PVプロジェクトは、砂漠化抑制、緑化、ひいては畜産業にも貢献するため、政府も力を入れています8)(広島に住む筆者としては、黄砂飛来の軽減も期待します!)。一方、需要地が遠いため「棄光」、「棄風」の問題が生じ、送電網整備等が行われたり、オフグリッド型のグリーン水素(アンモニア)製造プロジェクトも注目されています9)。こうした取組みが奏功して、2024年の非化石電力の設備容量は火力を上回り、その電力量も発電量の37%、エネルギー消費の20%を占めました10)。2025年目標を前倒し達成したことになります。
再エネ導入が飛躍的に進む一方で、エネルギー消費全体の伸びも堅調(前年比4.3%増)なため、化石燃料利用も伸長しています。2024年の石炭は生産・輸入とも過去最高、石油も前年比1.1%増で世界消費の16%を占め、天然ガスも前年より8%増えました10)。2030ピークアウトに向け、水素やCCUS技術の導入も進められていますが、技術やコスト面での課題があるそうです9)。また、当面は国内経済回復に注力するためCN化が停滞したり、対中デリスキング対抗の重要鉱物輸出管理厳格化が相手国のCN化遅延を招く などが心配です。
■ 2035に加え2040年のNDCも示して予見可能性を高めるも経済効率性が心配な日本
日本では2024/12に第7次エネルギー基本計画、GX2040ビジョン、地球温暖化対策計画案が策定され、2025/2に閣議決定されました。
第7次エネルギー基本計画11)では、2040年電力需要はDX、AI、データセンター等で2023年比2割増と見込み、再エネを40-50%に増やすこと、原子力の20%維持が明示されました。火力発電は30-40%とし、CCSや水素・アンモニアを使うことで、GHGを削減することが示されています。筆者が注目したのは、計画案が検討されてきた基本政策分科会の議論の中で、「エネルギーコスト」や投資に対する「予見可能性」がたびたび俎上に上ったこと、また再エネ電力のコストがLCOE(均等化発電コスト)だけでなく一部の統合コストを含めて示されたことです12)。LCOEでは最安のPVは、再エネ比率が高まるほど統合コストが嵩み、再エネ容量6割では最も高くなるとのことです。
GX2040ビジョン13)は、投資環境への不確実性が増す中、上記の予見可能性を高めるため中長期的なGXの方向性を官民で共有する目的で策定されました。産業構造、産業立地、エネルギートランジションのビジョンや個別分野の取り組み等が示され、その実現のためのエネルギー政策がエネルギー基本計画という位置付けです。産業立地の項では、脱炭素電源の近接地点等へデータセンターの立地誘導する「ワット・ビット連携」が示されました。再エネ電源であれば、蓄電設備や火力でのバックアップが不可欠になりそうです。資金面では、20兆円規模の移行債発行、段階的カーボンプライシング導入(2026年度からの排出量取引制度本格稼働、2028年度からの化石燃料賦課金導入)が示されました。日本でもCNのための負担増が本格化しそうです。
地球温暖化対策計画14)では、1.5℃目標に整合的で野心的な目標として、GHGの2035年度60%、2040年度73%削減が掲げられ、2035&2040NDCとして締め切りから8日遅れて国連に提出されました。もっとも締め切りまでに提出した国はわずか10ヶ国程度でした。パリ協定の枠組みが機能不全に陥ってしまう最悪のリスクも想起されます。
以上のように、主要国は2050CNの理想追求よりも自国ファーストの傾向を益々強めています。このような国際状況において、エネルギー価格でハンディを負う日本は、CNを追求しながらも、他国動向を踏まえた柔軟な対応と、効率的な(CO2低減効果が高い)CN技術の追求が必要と考えます。
(参考文献)
1) European Commission PRESS RELEASE EU closing in on the 2030 climate and energy targets, according to national plans
2) European Commission The future of_European competitiveness Part A, The future of_European competitiveness Part B
3) European Commission A Competitiveness Compass for the EU
4) European Commission The clean industrial deal A joint roadmap for competitiveness and decarbonization
5) 資源エネルギー庁 第69回基本政策分科会 エネルギーを巡る最近の動向について
6) アメリカ合衆国下院歳入委員会 The-One-Big-Beautiful-Bill-Section-by-Section.pdf
7) 中華人民共和国中央政府 国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知_节能与资源综合利用_中国政府网
8) 地球環境戦略研究機関(IGES)シリーズ激動中国 パリ協定後の気候変動政策:その44 躍進する中国再生エネルギー戦略(2)、その45 躍進する中国再生エネルギー戦略(3)
9) NEDO 中国の水素・カーボンニュートラルに関する動向
10) JOGMEC 中国のエネルギーコンパス、24年動向と今後の注目点
11) 経産省 第7次エネルギー基本計画
12) 資源エネルギー庁 第67回基本政策分科会 発電コスト検証に関する議論について概要)
13) 経産省 GX2040ビジョン
14) 環境省 地球温暖化対策計画
● コラム ~ トランプ2.0と欧州右派の親和性 ~
筆者が注目する欧州動向は、右派・極右の台頭です。G7メンバー国では、伊政権政党であるFdIをはじめ、独AfD、仏RN、英リフォームUKなどが上位の支持率を得ています。G7以外でもハンガリー、オランダ、等多くの国で右派・極右政権があります。これらの政党の多くは環境よりも経済を優先し、化石燃料を容認する立場です。欧州全体で見ても、2024/6の欧州議会選挙で環境政党は議席を減らし、中道右派~極右の右派勢力は半数を超える議席を得ました。2035年の内燃機関車販売禁止の見直しにも大きな影響を与えそうです。
一方、トランプ2.0の様々な施策は、反DEI(Diversity, Equity, Inclusion)、反ウォークネス※1、あるいはネオリアリズム※2的な側面を持ち、欧州の右派・極右と多くの共通点があります。ジョルジャ・メローニ伊首相の米大統領就任式出席、JDバンス副大統領のミュンヘン安全保障会議での欧州民主主義の方向性批判とそれへの欧州右派の賛同、当時トランプ氏支持のイーロン・マスク氏のAfD支援、リフォームUK干渉等、両者は親和性を高めています。この親和性およびトランプ大統領返り咲きの背景を踏まえると、自国経済優先や環境対応停滞は、トランプ大統領任期の4年間のみと言った一過性・短期の現象ではないように思います。
最後に2025/6に開催された第69回基本政策分科会でのお二人の委員のコメントを付記します。日鉄会長兼CEO 橋本氏 「トランプ大統領の次に誰がなっても変わらない」 「オープンでフェアーな国際貿易のルールに戻ることは想定できない」、NTT会長 澤田氏 「エネルギーだけでなく世界秩序の背景が変化しつつあり、おそらく戻らない」 「グローバリズム オンリー、環境重視の原理主義的世界から、各国が自国ファーストに舵を切っている」
※1.反ウォークネス:社会的正義や進歩的な価値観を過度に推進する「ウォークネス(Wokeness)」に対する批判的な立場
※2.ネオリアリズム:国際社会には絶対的な支配者がいないので、各国は自国の安全を守るために「力の均衡」を保てるよう軍事力や経済力を強化する
以前の投稿はこちら
カーボンニュートラルを考える
第1回 何故、カーボンニュートラル(CN)化が必要? 公開中
第2回 主要国・地域のカーボンニュートラル(CN)化への取組み 公開中